AI医療機器開発におけるISO 14971|リスクマネジメントから承認まで
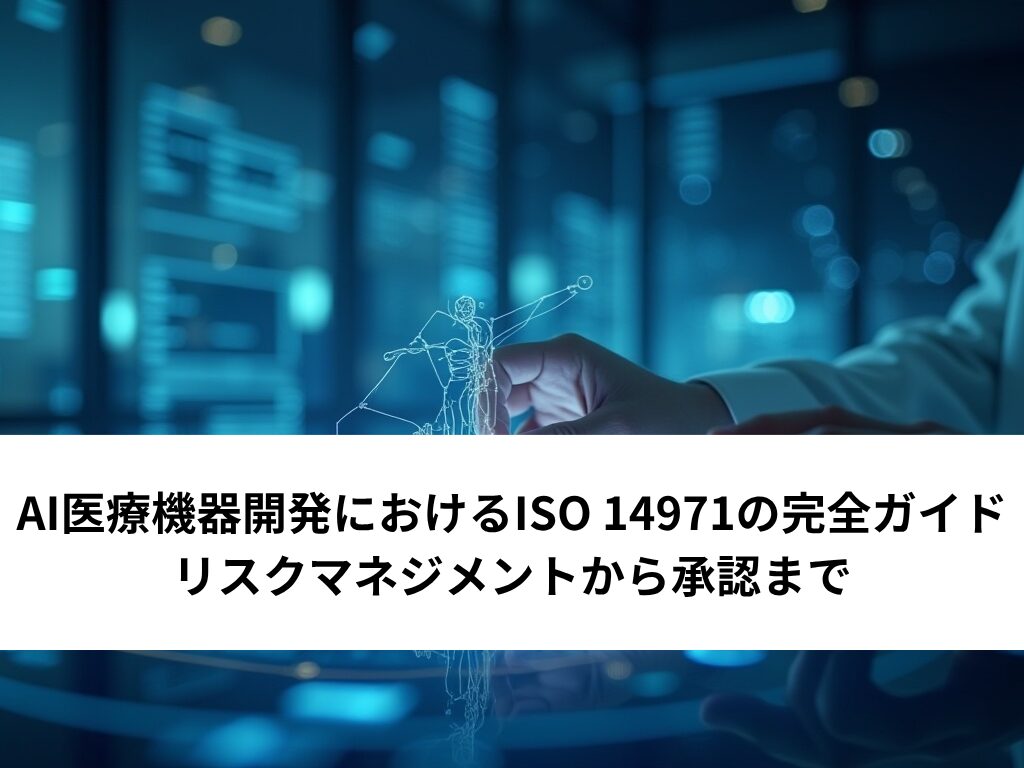
AI医療機器開発において、ISO 14971に基づくリスクマネジメントは承認取得の成否を左右する重要な要素です。PMDAによるAI医療機器の承認件数が急増する中、適切なリスクマネジメント体制の構築が市場参入の鍵となっています。しかし、「ISO 14971とは何か」「AI医療機器開発でどう活用すべきか」「PMDAガイドラインとの関係性は」といった疑問を抱える開発企業も多いのが現状です。
本記事では、AI医療機器開発におけるISO 14971の実践的な活用方法を、具体的な企業事例とともに詳しく解説します。株式会社AIメディカルサービスの「gastroAI-model G」やNTTデータのAI画像診断システムなど、実際の承認事例から学ぶリスクマネジメントの成功要因、医用画像診断支援システム開発ガイドラインへの対応方法、AI特有のリスク評価手法まで、開発現場で即座に活用できる実践的な情報をお届けします。
この記事を読むことで、AI医療機器開発におけるリスクマネジメントの全体像を把握し、承認取得に向けた具体的なアクションプランを立てることができるでしょう。
- ISO 14971とAI医療機器開発の関係性とPMDAガイドラインへの対応方法
- AI医療機器承認を取得した企業の具体的なリスクマネジメント事例
- 画像診断支援AIや医用画像診断支援システムの開発における実践的手法
- AI特有のリスク(データバイアス、ブラックボックス性)の評価と対策方法
- 開発プロセス全体でのISO 14971統合による業務効率化のポイント
ISO 14971とは?AI医療機器開発に不可欠なリスクマネジメント規格
ISO 14971は医療機器のリスクマネジメントに関する国際規格で、日本ではJIS T 14971として採用されています。
最新版のJIS T 14971:2020では、リスク関連用語の明確化、ベネフィット・リスク分析の強化、製造後情報の取扱いに関する詳細な要求事項が追加されました。この規格は、リスクの特定、分析、評価、コントロール、残留リスクの評価という体系的なプロセスを通じて医療機器の安全性を確保します。
ISO 14971の基本概念と医療機器への適用範囲
ISO 14971は、医療機器のライフサイクル全体を通じたリスクマネジメントプロセスを定義しています。ハザードの特定から始まり、危険状態の分析、危害の評価、リスクの推定・評価、リスクコントロールの実施、残留リスクの評価まで段階的なアプローチを採用します。
QMS省令第26条第3項では、製品実現に係る全ての工程における製品のリスクマネジメントに係る要求事項を明確にし、適切な運用を確立することが義務付けられています。
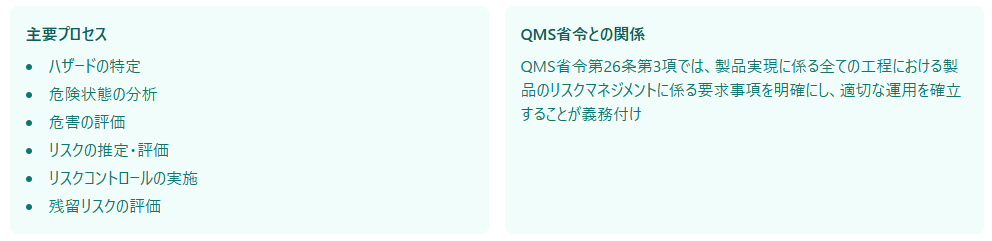
AI医療機器開発においてISO 14971が重要な理由
AI医療機器では、従来の医療機器にはない新たなリスク要素が存在するため、ISO 14971の適用がより重要になります。PMDAの報告書によると、AI利用医療機器分野における規格は3層構造(基礎規格、機能規格、特定用途規格)として整理され、基礎規格にISO 14971が含まれています。
AI医療機器の承認審査では、アルゴリズムの透明性、データの品質管理、継続的な性能監視が重要な評価項目となり、これらすべてがリスクマネジメントの枠組みで管理される必要があります。

ISO 13485との関係性と品質マネジメントシステムとの統合
ISO 14971は、品質マネジメントシステム規格であるISO 13485と密接に関連しています。ISO 13485では設計・開発プロセスにおいてリスクマネジメントの実施が要求され、ISO 14971はその具体的な手法を提供します。
AI医療機器開発では、品質マネジメントシステムとリスクマネジメントシステムを統合的に運用することで、開発効率の向上と規制適合性の確保を同時に実現できます。
 ReAlice株式会社 開発担当者
ReAlice株式会社 開発担当者AI医療機器の開発においては、従来以上にリスクの動的変化やデータ依存性が課題となります。ISO 14971は、これら不確実性を含むリスクを体系的に評価・管理する枠組みとして有効であり、設計初期からの導入が不可欠です。
AI医療機器特有のリスクとISO 14971による評価手法
AI医療機器には、従来の医療機器では考慮されなかった特有のリスクが存在します。これらのリスクは、AIの学習プロセス、データ依存性、アルゴリズムの不透明性に起因するものが多く、ISO 14971の枠組みを用いて体系的に管理する必要があります。
PMDAの調査によると、AI医療機器の承認審査において最も重要視される項目は、これらのAI特有のリスクに対する適切な評価と管理体制の構築です。
データバイアスと学習データの偏りによるリスク
学習データの偏りは、AI医療機器において最も深刻なリスクの一つです。特定の人種、年齢、性別に偏ったデータで学習されたAIは、診断精度に大きな差が生じる可能性があります。
株式会社AIメディカルサービスが開発した内視鏡画像診断支援ソフトウェア「gastroAI-model G」は、内視鏡検査中に生検等追加検査を検討すべき病変候補を検出し、医師の診断補助を行うシステムです。このシステムは2024年日経優秀製品・サービス賞のスタートアップ部門賞を受賞しています。
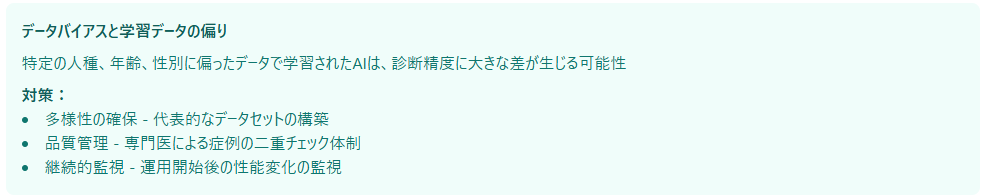
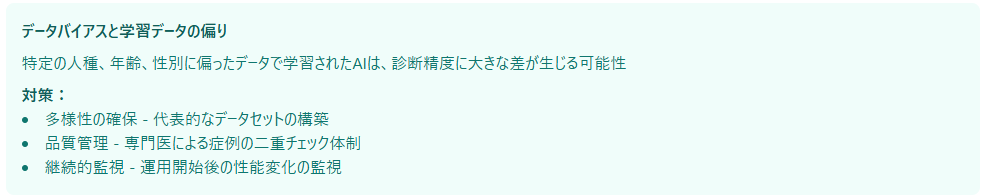
アルゴリズムのブラックボックス性と説明責任の課題
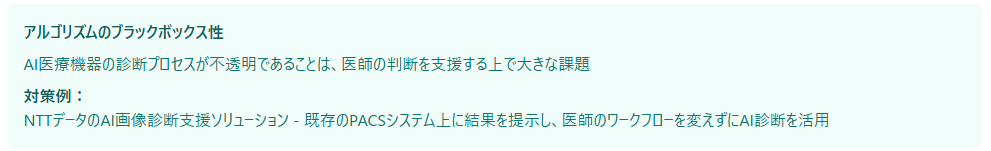
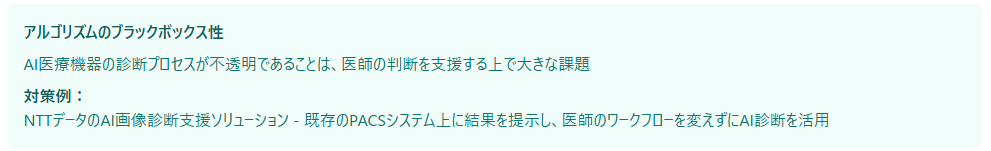
AI医療機器の診断プロセスが不透明であることは、医師の判断を支援する上で大きな課題となります。
NTTデータが開発したAI画像診断支援ソリューションでは、既存のPACSシステム上に結果を提示することで、医師のワークフローを大きく変えることなくAI診断を活用できる仕組みを構築しました。このアプローチにより、AI診断の根拠を医師が理解しやすい形で提示し、説明責任の問題に対処しています。
継続的学習とモデル更新に伴うリスク変化
AI医療機器では、運用開始後もデータの蓄積により性能が変化する可能性があります。この継続的な変化は、初期の安全性評価だけでは対応できない新たなリスクを生み出す可能性があります。
PMDAの専門部会では、市販後に性能変化することを意図するAI(Adaptive AI)の審査のあり方が重要な論点として検討されており、継続的学習によるリスク変化への対応が求められています。
このような課題は、AI医療機器における継続的なリスク管理と透明性確保の重要性を示しています。
サイバーセキュリティリスクと不正アクセス対策
AI医療機器は、ネットワーク接続により外部からの攻撃リスクにさらされます。
トヨタ記念病院では、AI問診システムの導入に際して、患者データの保護とシステムの完全性を確保するため、多層的なセキュリティ対策を実施しています。同院では2022年2月から呼吸器内科と消化器外科でAIタブレット問診を先行導入しており、タブレット端末を使用してAIが患者に問診を行うシステムを運用しています。
- 暗号化通信の実装
- 多要素認証システムの導入
- アクセス権限の適切な管理
- 定期的なセキュリティ監査
- インシデント対応計画の策定



AI医療機器は、その高度な自律性ゆえに、学習データの偏りや予測根拠の不透明性といった新たな課題を内包しています。これらに対しては、技術的な信頼性だけでなく、運用上の透明性や説明可能性の担保が鍵となります。
ISO 14971に基づくAI医療機器のリスクマネジメント実践手順
AI医療機器のリスクマネジメントでは、従来の医療機器開発プロセスにAI特有の要素を組み込んだ体系的なアプローチが必要です。
実際の開発現場では、3つのフェーズ(Use FMEA、Design FMEA、Process FMEA)との連携により、設計からのフィードバックを反映したヌケモレのないリスクマネジメントが実現されています。
AI特有のハザード特定と危険状態の分析
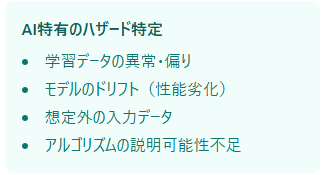
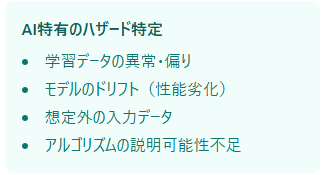
AI医療機器のハザード特定では、学習データの異常、モデルのドリフト、想定外の入力データなど、AI特有の要素を考慮する必要があります。
株式会社AIメディカルサービスの内視鏡診断支援システムでは、胃炎に似た早期胃がんの見逃しリスクを特定し、専門医でも判断が困難な症例に対するAI支援の有効性を検証しています。このシステムでは、多様な症例データベースを構築し、稀な症例に対する診断精度の維持を重要なハザード管理項目として位置づけています。
リスク評価における確率と重篤度の定量化手法
AI医療機器では、従来の故障率ベースの確率評価に加えて、診断精度の変動や誤診の可能性を定量化する必要があります。
NTTデータのAI画像診断ソリューションでは、腎臓を対象とした実証実験において、感度・特異度の統計的分析により診断精度を定量評価しています。この評価手法では、ROC曲線分析やクロスバリデーションを用いて、AI診断の信頼性を数値化し、臨床現場での受容可能なリスクレベルを設定しています。
感度・特異度・ROC曲線による診断精度の定量化
複数のデータセットでの性能検証による信頼性確保
臨床現場での実用性を考慮したリスクレベルの決定
設計段階でのリスクコントロール対策
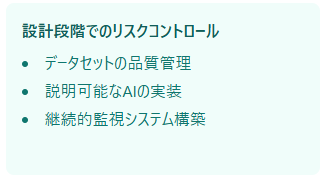
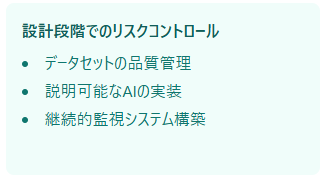
AI医療機器の設計段階では、アルゴリズムの選択、学習データの品質管理、検証手法の確立が重要なリスクコントロール要素となります。
トヨタ記念病院では、2022年2月から呼吸器内科と消化器外科でAIタブレット問診を先行導入しており、患者の回答をもとにAIが症状に合わせた質問を行うシステムを運用しています。このシステムでは、タブレット端末で質問に答えてもらい、症状を電子カルテに反映させる仕組みが実装されています。
データセットの品質管理と検証手法
AI医療機器の性能は学習データの品質に大きく依存するため、データセットの品質管理は最重要のリスクコントロール要素です。
株式会社AIメディカルサービスでは、内視鏡画像データベースの構築において、複数の専門医による症例の二重チェック体制を確立し、データの信頼性を確保しています。このプロセスでは、画像の品質評価、診断ラベルの正確性検証、データの多様性確保を体系的に管理し、学習データの偏りによるリスクを最小化しています。
- 専門医による二重チェック体制
- 画像品質の客観的評価基準
- 診断ラベルの正確性検証
- データの多様性確保
- 継続的な品質監視システム
説明可能なAIとアルゴリズムの透明性確保
医療現場でのAI活用では、診断根拠の説明可能性が重要な要求事項となります。
NTTデータのAI画像診断システムでは、診断結果とともに病変部位のヒートマップ表示機能を提供し、AI判断の根拠を視覚的に示しています。この機能により、放射線科医はAI診断の妥当性を迅速に評価でき、最終的な診断判断における責任の所在を明確化しています。
製造・運用段階でのリスク管理と継続的監視
AI医療機器では、運用開始後の継続的な性能監視が重要なリスク管理要素となります。
PMDAの専門部会では、市販後に性能変化することを意図するAI(Adaptive AI)の審査のあり方が重要な論点として検討されており、継続的な性能監視と透明性確保がAI医療機器における重要なリスク管理要素として位置づけられています。
- 診断精度の継続的評価
- データドリフトの検出
- ユーザーフィードバックの収集
- 性能劣化の早期発見
- セキュリティインシデントの監視



データ品質や説明可能性への配慮は、信頼性と臨床受容性の両立に直結します。設計初期からFMEAを通じて課題を洗い出し、運用中もデータ変化に応じて柔軟に対応できる枠組みを組み込むことが重要です。
AI医療機器の承認プロセスとPMDAガイドライン対応
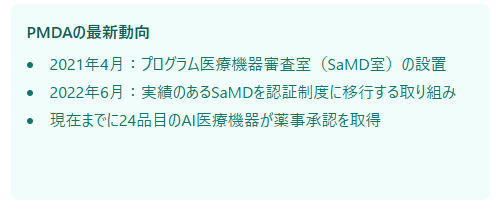
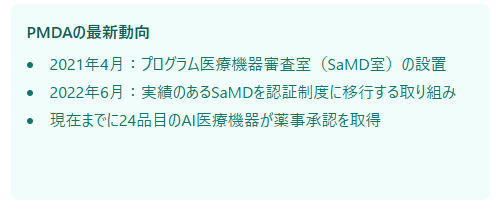
AI医療機器の承認プロセスでは、従来の医療機器審査に加えて、AI特有の技術的要素に対する評価が重要になります。
PMDAでは2016年以降継続的に、AI医療機器に関する複数のガイドラインを策定し、承認審査の標準化を進めています。現在までに24品目のAI医療機器がPMDAの審査を経て薬事承認を取得しており、今後さらなる承認品目の増加が期待されています。
PMDAによるAI医療機器承認の最新動向
PMDAでは、AI医療機器の承認審査において、アルゴリズムの妥当性、学習データの適切性、臨床性能の評価を重点的に審査しています。
2022年6月の規制改革実施計画により、実績のあるSaMD(Software as a Medical Device)を認証制度に移行する取り組みが進められており、承認プロセスの効率化が図られています。消化器内視鏡領域では、既に複数のAI診断支援システムが承認を取得し、臨床現場での活用が始まっています。
- 2021年4月:プログラム医療機器審査室(SaMD室)の設置
- 同時期:厚生労働省にプログラム医療機器審査管理室、薬事・食品衛生審議会にプログラム医療機器調査会を設置
- 審査ポイントの情報公表による開発事業者の予見性向上
医用画像診断支援システム開発ガイドラインの活用
PMDAが2019年5月に発行した「人工知能技術を利用した医用画像診断支援システム 評価指標」(令和元年5月23日付薬生機審発0523第2号)は、AI画像診断システムの開発と承認申請における重要な指針となっています。
このガイドラインでは、学習データの品質要件、アルゴリズムの検証方法、臨床性能評価の手法について詳細に規定されており、開発企業にとって承認取得の道筋を明確化しています。
データの多様性、品質管理、偏りの評価に関する詳細な要求事項
統計的性能評価、クロスバリデーション、実環境での検証手法
専門医との診断一致率評価、実臨床での有効性検証
承認申請におけるリスクマネジメントファイルの作成
AI医療機器の承認申請では、ISO 14971に基づくリスクマネジメントファイルの提出が必須となります。このファイルには、AI特有のリスク分析、データ品質管理手順、継続的監視計画などを含める必要があります。
開発プロセス全体のトレーサビリティを確保し、規制当局の要求に対応できる包括的なリスクマネジメント文書を効率的に作成することが重要です。
- AI特有のリスク分析結果
- データ品質管理手順書
- 継続的監視計画
- 変更管理プロセス
- 市販後安全管理計画
画像診断支援AIの承認事例と学ぶべきポイント
株式会社AIメディカルサービスの「gastroAI-model G」は、内視鏡画像診断支援システムとして承認を取得した代表的な事例です。この承認事例では、多様な症例データベースの構築、専門医による検証体制の確立、継続的な性能評価システムの構築が評価されました。
特に、胃炎に似た早期胃がんの検出という高難度な診断支援において、従来の診断精度を上回る性能を実証したことが承認の決定要因となっています。
- 多様な症例データベースの構築
- 複数施設からの症例収集
- 専門医による品質管理
- 専門医による検証体制の確立
- 二重チェック体制
- 診断一致率の評価
- 継続的な性能評価システム
- 市販後監視体制
- 性能維持メカニズム



PMDAの指針に沿ったデータの質管理や性能評価の透明性が審査の通過率を大きく左右します。
AI医療機器開発プロセスへのISO 14971統合方法
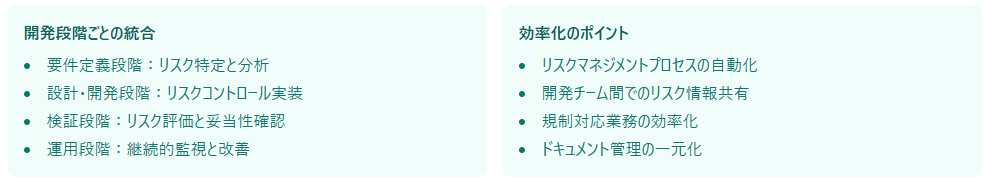
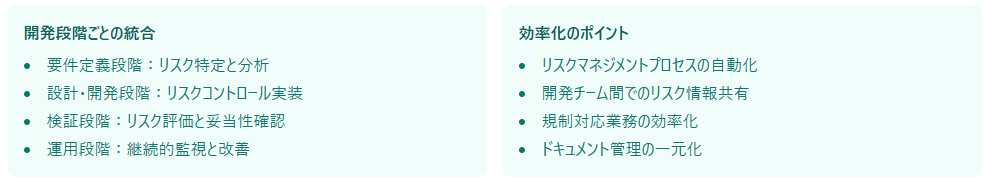
AI医療機器開発では、従来の医療機器開発プロセスにISO 14971のリスクマネジメント要素を体系的に統合する必要があります。
開発の各段階(要件定義、設計、検証、運用)において、AI特有のリスク要素を考慮したマネジメントプロセスの確立が成功の鍵となります。技術の見える化、判断の見える化、業務の見える化を連携させ、効率的なリスクマネジメントが実現できます。
要件定義段階でのリスク分析の組み込み
AI医療機器の要件定義では、想定される使用環境、対象患者群、診断精度要件などを明確化し、それぞれに関連するリスクを特定する必要があります。
トヨタ記念病院のAI問診システムでは、多様な患者層への対応、言語理解の精度、既存システムとの連携などを要件として定義し、各要件に対するリスク分析を実施しています。この分析により、システム設計段階での重要な設計判断基準が明確化されています。
想定される使用環境、対象患者群、診断精度要件の詳細定義
各要件に関連するAI特有のリスク要素の体系的な特定
リスク分析結果に基づく設計判断基準の明確化
設計・開発フェーズでのリスクコントロール実装
設計・開発段階では、要件定義で特定されたリスクに対する具体的な対策を実装します。
NTTデータのAI画像診断システムでは、既存のPACSシステムとの統合により、医師のワークフロー変更リスクを最小化する設計を採用しています。このアプローチにより、新システム導入による業務混乱のリスクを効果的にコントロールし、臨床現場での受容性を高めています。
検証・妥当性確認におけるリスク評価手法
AI医療機器の検証では、従来のソフトウェア検証に加えて、AI特有の性能評価が必要になります。
株式会社AIメディカルサービスでは、内視鏡診断支援システムの検証において、多施設での臨床評価を実施し、実環境での診断精度を検証しています。この検証プロセスでは、感度・特異度の統計的分析、専門医との診断一致率評価、稀な症例に対する性能評価を体系的に実施し、臨床使用における安全性を確認しています。
- 多施設での臨床評価実施
- 感度・特異度の統計的分析
- 専門医との診断一致率評価
- 稀な症例に対する性能評価
- 実環境での安全性確認
市販後監視とリスクマネジメントの継続的改善
AI医療機器では、市販後の継続的な性能監視が重要なリスクマネジメント要素となります。
PMDAの専門部会では、市販後に性能変化することを意図するAI(Adaptive AI)の審査のあり方が重要な論点として検討されており、継続的な性能監視と透明性確保がAI医療機器における重要なリスク管理要素として位置づけられています。このような継続的監視では、診断精度の追跡、データドリフトの検出、医療従事者からのフィードバック収集が重要な要素となります。



要件定義から市販後まで一貫した管理体制を構築し、AI特有の動的な性能変化にも対応可能な柔軟性を持たせることが求められます。
AI医療機器開発における業務効率化とリスクマネジメント
AI医療機器開発では、リスクマネジメントプロセス自体の効率化も重要な課題となります。従来の手作業による文書作成や管理では、開発スピードの低下や品質のばらつきが生じる可能性があります。
最新のデジタルツールやAI技術を活用することで、リスクマネジメント業務の自動化と標準化を実現し、開発効率と品質の両立が可能になります。
リスクマネジメントプロセスの自動化とAI活用
リスクマネジメント支援ツールでは、FMEAからのフィードバックを自動的にリスクマネジメントシートに反映する機能により、手作業による転記ミスや漏れを防止できます。
このシステムでは、Use FMEA、Design FMEA、Process FMEAの各段階で特定されたリスク項目が自動的に統合され、包括的なリスク評価が効率的に実施できます。
- FMEAからの自動フィードバック反映
- 手作業による転記ミスの防止
- リスク項目の自動統合
- 包括的なリスク評価の効率化
開発チーム間でのリスク情報共有システム構築
AI医療機器開発では、多職種のチームメンバー間でのリスク情報共有が重要になります。
トヨタ記念病院のシステム開発では、医師、看護師、システムエンジニア、品質管理担当者が連携し、各専門分野の観点からリスク評価を実施しています。このような多職種連携により、単一の視点では見落としがちなリスクを包括的に特定し、より堅牢なシステム設計が実現されています。
規制対応業務の効率化とドキュメント管理
AI医療機器の承認申請では、大量の技術文書と品質文書の作成が必要になります。
開発プロセス全体のトレーサビリティを自動的に記録し、規制当局への提出文書を効率的に生成できるシステムにより、文書作成工数の削減と品質の向上を同時に実現し、承認取得までの期間短縮に貢献できます。
- 開発プロセス全体のトレーサビリティ自動記録
- 規制当局提出文書の効率的生成
- 文書作成工数の大幅削減
- 品質向上と承認期間短縮の同時実現



AI医療機器のような複雑な開発では、自動化によって人為的エラーを最小化し、関係者間の情報整合性を保つ仕組みが求められます。ツールの導入は単なる効率化にとどまらず、開発全体の透明性と再現性を高める手段として有効です。属人性を排除し、規制要件への対応力も強化できる点が最大のメリットです。
ISO 14971開発AI×AIに関してよくある質問
AI医療機器のリスク評価は従来の医療機器と何が違いますか?
AI医療機器のリスク評価では、アルゴリズムの不確実性、学習データの偏り、継続的な性能変化など、AI特有のリスク要素を考慮する必要があります。
株式会社AIメディカルサービスの内視鏡診断支援システムでは、従来の機械的故障リスクに加えて、診断精度の変動、データバイアスによる誤診リスク、アルゴリズムの説明可能性に関するリスクを体系的に評価しています。これらのリスクは確率的な性質を持つため、統計的手法を用いた定量評価が重要になります。
機械的故障、電気的故障、材料劣化などの物理的リスクが中心
データ品質、アルゴリズムの透明性、継続的な性能変化などの論理的リスクが追加
ISO 14971はAI医療機器開発のどの段階で適用すべきですか?
ISO 14971は、AI医療機器開発のライフサイクル全体を通じて継続的に適用する必要があります。
トヨタ記念病院のAI問診システム開発では、要件定義段階でのリスク特定から始まり、設計・開発、検証、運用、変更管理の各フェーズでリスクマネジメントを実施しています。特にAI医療機器では、運用開始後のデータ蓄積による性能変化に対応するため、市販後監視段階でのリスクマネジメントが重要になります。
- 要件定義段階:リスク特定と分析
- 設計・開発段階:リスクコントロール実装
- 検証段階:リスク評価と妥当性確認
- 運用段階:継続的監視と改善
- 変更管理:リスク再評価
AI医療機器のバリデーションはどのように行えば良いですか?
AI医療機器のバリデーションでは、従来のソフトウェアバリデーションに加えて、AI特有の性能評価が必要です。
NTTデータのAI画像診断システムでは、多施設での臨床データを用いたクロスバリデーション、専門医との診断一致率評価、実環境での性能監視を組み合わせた包括的なバリデーション手法を採用しています。このプロセスでは、感度・特異度の統計的分析、ROC曲線による性能評価、継続的な性能監視システムの構築が重要な要素となります。
- 多施設での臨床データ検証
- クロスバリデーション実施
- 実環境での性能確認
- 専門医との診断一致率評価
- 感度・特異度の統計的分析
- ROC曲線による性能評価
- 継続的な性能監視
- 市販後性能監視システム
- 性能劣化の早期検出
PMDAはAI医療機器についてどのようなガイドラインを出していますか?
PMDAは「医用画像診断支援システム開発ガイドライン」(2019年5月)をはじめ、AI医療機器に関する複数のガイドラインを策定しています。
これらのガイドラインでは、学習データの品質要件、アルゴリズムの検証方法、臨床性能評価の手法について詳細に規定されており、ISO 14971と整合させながら開発を進める必要があります。
また、2022年の規制改革計画により、実績のあるSaMDの認証制度移行も進められており、承認プロセスの効率化が図られています。
2019年5月発行、AI画像診断システムの開発と承認申請の指針
継続的な性能変化などのAI特性に即した評価手法の検討
変更計画を含む承認制度、市販後再学習による性能向上を支援
AI医療機器のリスクマネジメントにおいてデータマネジメントはどのように重要ですか?
AI医療機器の性能は学習データに大きく依存するため、データマネジメントはリスクマネジメントの中核要素となります。
株式会社AIメディカルサービスでは、内視鏡画像データベースの構築において、データの品質管理、偏りの評価、匿名化処理、継続的な品質監視を体系的に実施しています。
このプロセスでは、データの収集から保管、利用、廃棄までのライフサイクル全体での管理が必要であり、個人情報保護法やGDPRなどの法規制への対応も重要な要素となります。
- AI性能の直接的決定要因
- データ品質がリスクレベルを左右
- 偏りが診断精度に重大な影響
- 法規制遵守の必須要件
- 継続的な監視と改善が必要


